
いまや日本の夏の風物詩ともなっている、「お盆帰り」という名の民族の大移動。
毎年のように映し出される、高速道路の大渋滞や、各交通機関の混雑ぶりや、空港や駅などで見かける、田舎のおじいちゃん、おばあちゃんと可愛い孫との微笑ましい再会のシーン等々。
でも、それはそれで「いとをかし…」という趣もあります。
では肝心の、この「お盆」の習慣は、一体どのようにして生まれたのか、その起源や由来をあなたはご存知でしょうか?!
そこで今回は、お盆の習慣の起源といわれている、仏教説話をご紹介したいと思います。
餓鬼の世界で苦しむ母をご回向で救った目連尊者のお話
お釈迦様には、たくさんの優秀なお弟子さんがいました。
その中でも、神通力が一番優れた方で「目連(もくれん)」とういお弟子さんがいました。
ある日、目連さんは、幼いころに亡くなったお母さんにお会いしたくなり、神通力を使って探してみようと考えました。
目連さんは、自分はお釈迦様のもとで仏道を修行しているのだから、

と考えていました。
そう思って神通力で、まずは仏様の世界(仏界)を探してみました。
けれども、そこにはお母さんの姿は見当たりませんでした。
次に、菩薩界、天上界…。
人間の住む娑婆世界で、徳を積んだものだけが行けるといわれている、あの世の世界を探してみましたが、どの世界にもお母さんの姿は見当たりませんでした。
まさかとは思いましたが、目連さんは※1「餓鬼の世界」をのぞいてみることにしました。
餓鬼の世界では、骨と皮だけになってやせ衰え、お腹だけがプーッとをふくれあがり、のどは針のように細くなっている、たくさんの餓鬼がうごめいていました。

さも娑婆世界で、さもしい行いをしていたんだろうな…。
と憐れんでいた瞬間、
目連さんの目に、まさかの光景が飛び込んできました。
それは、あの愛おしいお母さんの変わり果てた姿だったのです。
※1餓鬼界:貪り食ったり、物おしみをしたり、他人をねたんだりした悪行行為が因果となって堕とされていく世界
娑婆世界での報いがあの世での分岐点になる
実はその姿は、目連さんのお母さんが、目連さんを育てる過程において、人の目をごまかすようなインチキや悪どい商売をして人をだましていたという、娑婆世界での報いだったのです。

そう思った目連さんは、神通力でいっぱいのご馳走を送って届けてやることにしました。
しかし、お母さんが、目の前のご馳走に飛びついて、わしづかみで食べようと手をだそうとした瞬間、ご馳走は、激しい炎となって燃え上がってしまいました。
その光景をみた目連さんは、ビックリして慌てて神通力で水をかけようとしましたが、火は消えるどころか、油を注いだように一層燃え上がってしまうのです。
そして、お母さんはそのあまりの熱さに一層苦しむばかりでした…。
失望し落胆した目連さんは、お釈迦様のところに行って、これまでのいきさつを包み隠さず申し上げて教えを乞うことにしました。
ご回向こそが亡き精霊・ご先祖への一番の贈り物
お釈迦様は、諭すようにおっしゃいました。

汝の母の娑婆世界での罪は大変重たいものだったようだ…。
今の汝の母の状態を、汝の力だけで救おうとするのは到底無理なことだ。
汝の母を救うには、現世で修業している僧や、仏道を信行している信者たちに、心からのご供養をするとよいであろう。
そうすれば、その行いが功徳となって、必ずや汝の母は餓鬼の苦しみから逃れ救われよう…。
と。
それから目連さんは、お釈迦教え通りに、たくさんの修業僧や信者さんたちに、心を込めてご供養をし、ご回向をしました。
その結果として、この目連さんの「功徳」が、「回向」となって目連さんのお母さんに振り向けられ、お目連さんお母さんは餓鬼の世界からのがれることができました。
というお話です。
目連尊者の仏説から学ぶこと
親孝行された目連尊者のお話、いかがだったでしょうか?
この目連さんの仏説から学ぶこととして、亡き精霊を救うには、ご先祖や亡き精霊を敬い、供養しご回向すること大事だということがあげられます。
そして一番良いことは、

 核家族化が進んでお久しい現代において、部屋に仏壇を配置したり、毎日お墓にお参りしたりすることは無理なことかもしれません。
核家族化が進んでお久しい現代において、部屋に仏壇を配置したり、毎日お墓にお参りしたりすることは無理なことかもしれません。
だからこそ、せめてお盆くらいは、ご先祖や亡き精霊を供養することが大切だと、教えて頂いているのではないでしょうか!
※回向の意味やその効用の詳細を、仏教マーケティング的観点から下記の記事で解説しています。
合わせて読むことで、いっそうお盆帰りが身近になり、その大切さが理解できることと思います。
最後までお読みいただき有り難うございました。

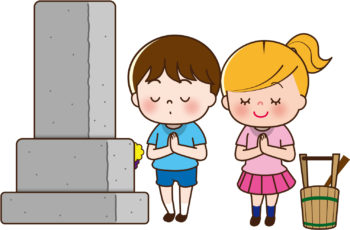


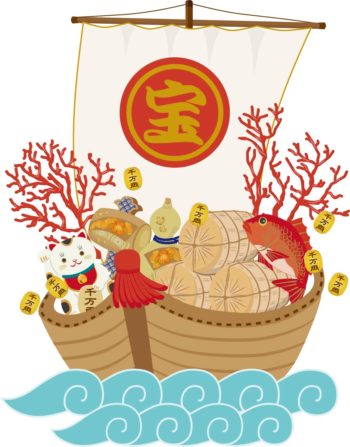

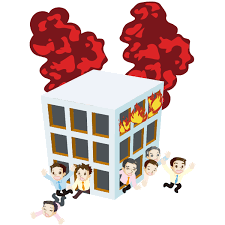
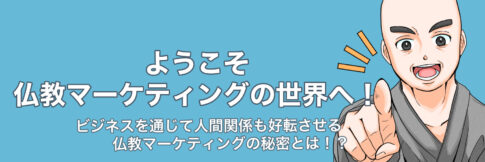



仏教マーケティング・アドバイザーのコージリです。